

|
|
|||
| ブランケット版・一般新聞のレイアウト・デザイン | |||
| ●「文字組み」をメーンとする組み版の中で最大のスペースを有する「ブランケット版」の「一般新聞」には、あらゆるデザインテクニックが詰まっています。 ●大きくは、編集管轄面と広告管轄面に分けられますが、広告は「デザイン業界」と直結しています。広告には、編集と異なった価値観・思想によったセオリーがあり、このセオリーこそ「狭義」デザインのセオリーです。 ●デザインはしかし、広告やポスターなどの独壇場なのでは、決してありません。新聞の編集管轄面にも、デザインが要請されており、近年、急テンポでデザイン化の波が押し寄せているのです。 ●「新聞レイアウト」にも、デザイン化がはじまっているのです。編集&レイアウト&デザインは、もはや切り離そうとしても切り離せない一連の仕事になりました。 ●究極のところ、「ジャーナリズム」でさえ、デザインを要請している(デザインが要請されている)、とさえ言えます。 |
|||
| ■レイアウト・10種類の部品 | |||
| ①本文 ②前文 ③キャプション(絵解き・写真説明) ④見出し ⑤表組(グラフ) ⑦イラスト(カット) ⑧写真 ⑨罫 ⑩余白 *色 |
|||
| ●新聞レイアウトの部品は10種類に分類できます。これらの部品は、雑誌ほか、あらゆる印刷メディアにも共通するものすが、ブランケット版・一般新聞では、それなりに特徴をもって使われ、雑誌でもそれなりの特徴をもって使われ、まったく異なった使われ方をしたり、あるいは微妙なテーストの違いをもって使われたりしています。 ●たとえば「罫」ひとつ、新聞でしか使われなかったり、「見出し」ひとつ、雑誌と新聞とでは異なった形で使われたりしてきました。雑誌の「余白」と新聞の「余白」もまるで違う扱いをされてきましたし、「色の使い方」だって、新聞と雑誌では異なります。 ●文字組みをメインとするメディアの中で、一般新聞・ブランケット版は、ページあたりのスペースが最大です。最大のスペースを持つ紙メディアのデザイン・レイアウトには、部品の扱い方にさまざまな特徴があります。それは、新聞の歴史とともに変化し、進化してきましたし、いまなお、日々、進化し、変化しています。こうして部品の扱いひとつ、古めかしく感じられる扱い方、斬新に感じられる扱い方の落差が生まれています。 ●新聞のレイアウト・デザインは、これらの部品を、1ページ全体の中で組み立てる作業です。創造的に配列し、メッセージを伝えようとするものです。とりわけ、意味性をもつ文字と画像物によって、メッセージを伝えようとする傾向にあります。ズバリ! 見出し&記事&写真の3本柱によって、メッセージを伝えようとしてきた歴史があるといってよいのです。 ●記事・見出&と写真以外の「イラスト」「表」「グラフ」「罫」「余白」「色」などが、だからといって、おろそかにされるべきものでもありません。最近では、これら部品のトータルなデザイン・レイアウトを志向する紙面が活発になっています。「罫」ひとつ、「グラフ」ひとつに、かなり細心な注意が払われるようになりました。あくまで、「見出し&記事&写真」は、主役でありますが、その他の部品をおろそかにする傾向は見られなくなりました。 ●「独立単面」を原則とする新聞のデザイン・レイアウトは、そのページで完結するものです。見開き面(ワイド面)は、ブランケット2ページを広げたときに、その2ページを独立した面として扱うものです。この「独立単面」という考え方は、新聞社の機構の問題ともからんでいますが、デザインの統一感という考え方と反しています。そこで。全ページのデザインに統一感を持たせようという動きがはじまりました。全ページを通じた「アートディレクション」という考え方を、各紙が取り入れはじめたのです。こうして、新聞のトータル・デザインニングの考えが、新聞の編集方針のイメージ戦術・戦略へと繋(つな)がりつつあります。と |
|||
| ■部品とデザイン(レイアウト) | |||
| ●部品はあくまで部品です。デザインは、部品の集合。意識的に、計画的に構成され、配列された全体です。 ●部品は全体のために存在し、全体は部品のために存在してはならないのが、デザインなのです。 ●部品のそれぞれが高品質で立派であっても、配列・構成にコンセプトがなく、イメージが拡散している紙面はデザインとしては落第です。(紙面)デザインは、イメージの集中を意図するものです。そのために部品が存在することを、肝に銘じておかなければなりませんが、いっぽう、ジャーナリズムを使命とする新聞には、個々の記事(部品)の主張が何よりも大事だ、という「アイデンティティー」に関わる命題が存在します。視覚的なトータリティーよりも、個々の記事のコンテンツ(内容)のほうが大事だ、という考え方が、ここでデザインと衝突するのです。こうして、二分法的、二元論的志向を、新聞は乗り越えられないでいます。 ●DTPソフトのめざましい進化が、「だれにでもできるデザイン」を促進しています。だれでもがデザイナーになり、編集者になれる時代になったのです。まさに「デザイン・デモクラシー時代」の到来です。しかし、そのことで、部品ばかりが立派な「ダサイン」が充満するようにもなりました。その一つの原因が、レイアウト・セオリーの欠如です。 ●「だれでもができるダサイン」から「だれでもができるデザイン」へのステップ・アップのためには、「何を表現したいのか」をじっくり考えてみる時間をとる習慣をつけたいものです。部品作成に手間ひまかけて、全体の構成・配置をおろそかにする傾向がありはしないか、を自問してみる必要があります。マシンの前に座りっぱなしで、「鉛筆」でラフを描く時間を省略していては「ダサイン」から脱皮できません。ラフを描きながら、「イメージする力」「想像力」を動員して、レイアウトをつくりあげていくことがポイントになります。 |
|||
| ●「ラフを描く」にはどうしたらよいでしょう、という疑問がわいてきた人は、すでに「デザインの中」に入っています。これは、「文章をどうやって書いたらいいのでしょう」という問いに似ているのです。 ●「自転車に乗れるにはどうしたらよいのでしょう?」「海で泳げるようになるにはどうしたらよいでしょう?」という問いとも、共通しているところがあります。 ●「習うより、慣れろ!」という段階が、モノゴトにはあるのです。何度も何度も、溺れかかりそうになり、いつしか人は泳げるようになっている。何度も何度も倒れ、身体中に傷を負いながら、ある日、自転車を漕いでいる自分に気付く――という瞬間に至るまでの「量」。時間の量、経験の量――。。「量の質的転換」という「運動の原理」です。 ●これを「弁証法的発展のセオリー」といいます。「弁証法的発展のセオリー」は、単純な段階論では説明がつきません。階段をひとつひとつ上っていくような運動の法則というよりも、ある日、突然、できちゃっている! ある時、目から鱗が落ちている!というような「発展の法則」なのです。 ●この「発展」を可能にするのは、あくまで「量」「時間」です。たゆまざる努力です。この線ではなくあの線だ、この言葉ではなくあの言葉だ、などと、血眼になって表現を選ぶ、あれかこれかを選び取る努力の果てに、この「発展」があることを信じましょう。 |
|||
| ■本文のレイアウト・デザイン | |||
| ①流し ②たたみ(&囲み) ③流したたみ ④ヨコ組み ⑤その他 ●本文を、レイアウトされた形から見ると、 ①流し ②たたみ(囲み) ③流したたみ の3種類に区分できます。③は、①②が共存している形です。 だから、形は2種類ある、それは「流し」と「たたみ」と覚えたほうがよいかもしれません。 ●「流し」は、水が流れるように、「右上」から「左下」へ向かって、記事が流れていく形です。漢字かな混じり文である日本語を縦組みした場合、上流は右上、下流は左下なのです。この流れは、モノ(写真とかイラストとか見出しとか)にぶつかれば、右下へ落ち、左に向かって流れ、またモノにぶつかれば右下に落ちてゆき、最後はブランケット紙面の左下に辿りつくのです。
●「たたみ」は、結果的に、矩形になる記事の形です。2段の矩形であれば、2段たたみ、3段の矩形であれば3段たたみ……となります。 ●「囲み」は、たたみの周囲を罫で囲んだもので、2段囲み、3段囲み……7段囲み……とさまざまに作ります。 ●「流したたみ」は、流した記事がモノにぶつかり、右下に落ちるとき、その落ちた分を2段にたたんだり、3段たたんだり……して、その記事の終わりをたたみにすることをいいます。 ●本文記事は、以上のいづれかの形になりますが、この他に、部分的に④横組みする場合もあります。 ●レイアウト・ベースが縦組みの場合、その縦組みページの中の一部を横組みにすることが可能です。これは、縦組みだからできることです。横組みベースのレーアウトの中に、縦組みを配置することはまずありません。縦組みのほうが、レイアウトの柔軟性が高い、とよく言われるのは、ひとつに、横組みを配置できるという点にもあるからです。 |
典型的な「流したたみ」の例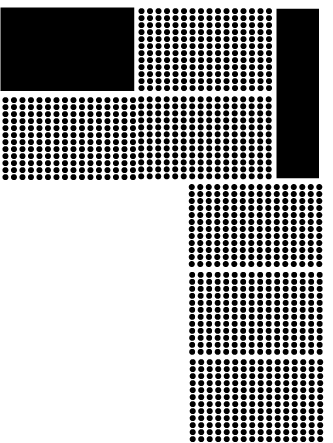 |
||
| ■流し・流したたみの衰退と新聞のアイデンティティー | |||
| ●モノ(写真やイラスト・見出し・表など)にぶつかったら、右下に落ちてゆき、左に向かって流れて、またモノにぶつかったら右下に落ちてゆく記事の「流し」は、時には、「うなぎの寝床」」のような形になります。これを、「読みづらい」と知覚する批判が起こりはじめています。 ●「流したたみ」は、はじめ、降版(印刷に回すこと)時間に余裕がない日刊新聞の製作現場で編み出された「組み版」技術でありました。それが、整理マン(レイアウトをしたり、見出しをつけたり、記事にチェックを入れたりする記者)の割り付けテクニック、レイアウト・テクニックに進化を遂げたという歴史があります。 ●活版時代に、整理マンのレイアウト指示(割り付け)に従って、鉛の活字を組み上げていく作業を「大組み」と呼んでいました。この時代、両手の10本の指を巧みに使って、15字30行、つまり活字を450本ほどを一気に掴んで、大組台の中に入れ込んでいく「大組」という作業は、建築にたとえれば「棟上げ」に似た、緊迫感と達成感の交じり合うワクワクする瞬間でした。 ●印刷時間が迫っている、あと30分でブランケットのスペースを活字で埋め尽くさなければならない。そんな時間の中での「大組」のテクニックのひとつが「流したたみ」でした。モノにぶつかって、右下に落ちた記事の、その落ちた行数を「タタミ」にすることによって、次の記事の見出しスペースを作るのです。立ち会っている整理記者のレイアウトには、行数計算が正確でない場合が時としてあり、大組作業者に「叱咤(しった」されながら、結局は「双方の」協働意志で記事末尾をタタムのです。新米の整理マンだと、怒鳴りあいになるケースもありましたが、双方おおむね「呼吸」を合わせ、流したたみが作られていったものでした。 ●「流したたみ」は、組み版に想像を絶する手間ひまのかかる活字・活版印刷時代の、しかもなお降版作業(印刷へ回す)の時間が極めて不足しているという制約から生まれた「現場のレイアウト・テクニック」であったのです。それが、「拙速主義」であらざるを得ない時代の「レイアウト・テクニック」として定着し、発展し、大いに活用されてきたのです。 ●CTS(Cold Type System、Computarized Type Setting))というコンピューター化がはじまっても、「流し」や「流したたみ」がなくなることはありませんでしたが、近年、きわめて少なくなったことは事実です。「たたみ」「囲み」など、コンピューター化された紙面製作システムによって、組み版のスピード化が図られ、「流し」「流したたみ」以外のレイアウト・テクニックが容易に使われるようになったのです。その結果、紙面のモジュール化、矩形化が進み、外観的には、雑誌レイアウト・デザインの流入という現象を生んでいます。いっぽう、新聞整理の現場で固守されてきた古い伝統的なセオリーへの反省も生まれ、「禁じ手」の再考、「禁じ手からの解放」の動きも盛んになっています。 ●①読みづらい、②見た目に古めかしい……など、「流し」や「流したたみ」への反省・再考は、主に、読み物面(フィーチャー面)、特集面など、記事をまえもって準備できる紙面から実行されています。2003年2月現在、朝日新聞の土曜日付けサービス版「Be on Saturday」は、どの面を見ても、「流し」「流したたみ」は皆無であり、全ての記事が「矩形」「モジュール」の中におさまっています。 ●この流れは、次第にニュース面にも及んでおり、ここにきて、「見出しのチドリ」などへの再考論議にもいたって、「新聞のアイデンティティー論」への発展を見せるようにもなりました。新聞の「デザイン化」は、「新聞のアイデンティティー」と切り離せない、緊急で重大な課題として浮上してきたのです。 |
|||
| ■モジュール化、矩形化レイアウトの浸透 | |||
| ■前文のレイアウト・デザイン | |||
| ●前文(リード)は、「レイアウト便利もの」です。さまざまな形を作ることが可能で、レイアウト全体の調整役として活用できるのです。「レイアウトに困ったときの前文」です。 |
●前文(リード)は、編集(者)の力量を問われるところであり、腕の見せどころでもあります。記事本文の要約である場合が多く、この要約をさらに要約したのが見出しと言うこともできるのです。見出し、前文、本文の3段構えで、読者に、わかりやすく記事を読ませるための装置になっているのです。 ●本文記事は記者が書き、前文は編集・整理部門が書き、見出しは整理部門がつくる、というように分業される場合が多いのですが、有能な記者がつけた「仮見出し」がそのまま、新聞紙面を飾ることもあります。 ●前文も、記者が書き、編集・整理者が、手を入れて仕上げるのが原則になっています。 |
||
| ■キャプションのレイアウト・デザイン | |||
| ●「写真説明」、「絵解き」などとも言う。 ●キャプションひとつ、さまざまなレイアウトの方法がある。 ①写真の上下左右。 ②上下左右でも、上付き、下付き、中央置き ③上付き、下付きでも、改行を入れ、「余白」を作る ④罫を巻く。円で巻く。直線で巻く(囲む) ⑤キャプションの中に「見出し」を入れる ⑥組み写真(複数の写真)のキャプションを一ヶ所に置く ⑦アミをかける ⑧写真の中に埋め込む |
|||
| ●表組み&グラフ | |||
| ●イラストのレイアウト・デザイン | |||
| ■見出しについてのあれこれ | |||
| 見出しのデザイン |
①見出しを作る ②見出しの形を作る ③見出しのレイアウト ④見出し論 |
||
| 写真のレイアウト | |||
| 罫のレイアウト | メントー、ヤマ・シキリの区別が消えた! | ||
| 余白のレイアウト | |||
| 色について | |||
| ■新聞レイアウトの牙城<チドリ> | |||
| ●2003年1月19日の朝日新聞第1面トップ見出しを、Illustratorで復元してみました。天地(=縦)5段抜き見出しです。こういう「並び」の見出しが、新聞見出しの特徴であり、他の媒体ではほとんど見られません。 ●これが、「チドリ」と呼ばれる新聞見出しの「並び」「置き方」「作り方」です。 ●「養育費、給与天引き可能に」を「主見出し」、「将来分差し押さえ」を「袖見出し」、「離婚で法制審方針」を「地見出し」と呼んでいます。 |
 |
||
| ●「チドリ」とは、主見出しと袖見出しの並びが、「斜」を描いた状態を指す、新聞制作現場「門外不出」の伝統的な「技」です。 ●「千鳥足」「浜千鳥」の「千鳥」から由来していることは、ほとんどまちがいないことでしょう。「千鳥」という鳥は、両足を並べて立つことが少なく、常に、「一歩を踏み出した」格好で立っています。敵から、身を守る姿勢であり、攻撃の姿勢でもあります。いつでも、攻守どちらへも転じられる姿勢なのです。片方の足が、もう一方の足と並んでいない状態です。 ●柔術、合気道など、日本の古武道の基本姿勢にも、この「千鳥」という姿勢があります。 ●「千鳥足」は、酔っ払いの足どりですが、これも、乱れた足並みながら、両足が並ぶことのない姿勢です。 ●いつだれが、そう名付けたのか不明ですが、新聞整理、新聞制作の現場で、見出しの並びの形が「千鳥」の姿勢に似ていることから、右の例の形を「千鳥」「チドリ」と呼んだのです。 ●見出しの並びにおける「チドリ」は、新聞レイアウトの「命」として、見出しのみならず、記事の配列、罫、写真の配置などへと応用されていきます。新聞デザインの「命」であり、「アイデンティティー」と言って過言でない「技」であり「思想」でもあります。 ●近年、新聞レイアウトのデザイン化が進み、「チドリ」は消えかかろうとしているかに見えますが、そうなった時には、新聞デザインのアイデンティティーが失われる、という見方があります。(アートディレクターの東盛太郎さんは、新聞デザインの根源を支える「チドリ見出し」が、本阿弥光悦が俵屋宗達の絵に書いた「散らし書き」の構図にまで遡(さかのぼ)る、という「新聞デザインのアイデンティティー論」を展開しています。 ●当「1億3000万人の編集・デザイン」の編集人も、似たような見解をもち、その淵源を千利休の「茶室」、千利休の茶道を世界に知らしめた岡倉天心「茶の本」の日本文化論に求めます。 ●「チドリ」には、おおげさに言えば、新聞デザインの過去・現在・未来がかかっているのです。 |
 |
||
| ●新聞は「チドリ」。 |  |
||
| ●雑誌は、「頭揃え」。 |  |
||
| ●新聞、それも一般新聞の制作現場では、「チドれ」「チドったほうがいい」「ここはチドるな」などという言葉がいまでも飛び交っています。 | |||
| ●「チドリの誕生」は、これかもしれません。 ●活版時代の新聞見出しは、文字数の制約がきびしく、「2行見出し8本10本」の大鉄則がありました。「鉛活字」は、全て「正体」で、サイズの種類も限られていましたから、1段に入る数、2段に入る数、3段、4段……に入る数は、自ずと決っていたのです。 ●整理マン、編集マンは、「見出しをとる」とき、指折り数えて、文字数が「主見出し8本、袖見出し10本」になるように、頭をひねります。 ●現在でも、「簡潔、明快」を旨(むね)とする見出し作りは、文字数を念頭にいれ、語呂(ごろ)よく、「こくがあり、味があり、インパクトの強い」言葉を探すため、日夜、「苦闘」が繰り広げられています。さながらその光景は、句会における「俳人」たちのようです。 ●デジタル・フォント化した新聞文字は、今では、簡単に、「平体」「長体」「斜体」をかけられますから、文字数制限はゆるくなっています。「8本10本」は、「9本11本」になり、何文字でもOKという時代になりつつあるのです。 ●50%平体、2倍長体も見られるようになりました。新聞レイアウト・デザインは、見出しひとつとっても、時代の波をかぶっているというわけです。 |
 |
||
| チドリの危機(きき)あるいは崩壊(ほうかい) | |||
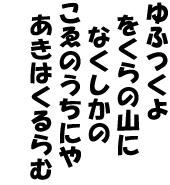 |
|||
| チドリの跳梁(ちょうりょう) | |||
| ●非対称とシンメトリー | |||
| ●「2段囲み」の1例。 | 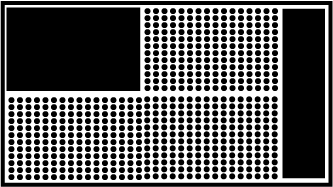 |
||
| ●ここで、注目しておきたいのは、囲んでいる「罫」の形です。「囲み」には、「4方囲み」「3方囲み」「2方囲み」とありますが、これは「3方囲み」です。 ●「3方囲み」の、「罫」の形に「チドリ」の考え方を取り入れたのが、この例です。 |
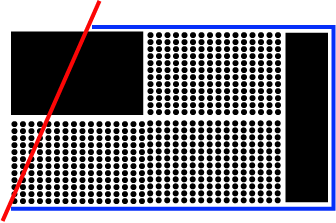 |
||
| ●なぜ、「チドリ」なのだろうか? | ①動的な感じを与える、動きを感じさせる。 ⇒ニュースらしく感じさせる。ニュース記事、ニュース面で使うデザイン・レイアウトの技法になった。 ②余白をつくる技法。主見出しと袖見出しを「チドる」ことによってできる余白は「優しい」「柔らかな」感じを与える。「頭揃え」は、「硬い」感じ。 ●例えば、直立不動の人の姿は、「頭揃え」のイメージであるし、「足を一歩踏み出している人の姿勢」は、「チドリ」のイメージである。 ③「不均斉」を好む日本人の美意識の現われ。 |
||
| アートディレクター東盛太郎の「千鳥」考 | |||
| *当サイト編集人と東さんとのメールのやりとりの中の1節から、東さんの考察のほんの「さわり」をここに紹介します。(右の欄) | 確かに千鳥は、日本の文化においてすばらしい、世界に類を見ないものではありますが、物事を論理的に伝えるやり方にはふさわしくないのでは、と常々疑問
を感じています。 千鳥は和漢混交体の和歌の情緒的表現をその原点としているので、新聞 見 出しにおいて、情緒性が必要かどうかが問われて、始めて議論すべき問題というふうに考えています。 たしかに初期の四行千鳥見出しは、情緒たっぷりのものでした。 商品としての新聞が面白い読み物(たとえニュースであっても情緒たっぷ り)として存 在してきた事の結果でもあります。 日本人の論理的思考の希薄さは、物事を情緒でとらえる日本人のアイデンティティと 重 なっているもので、初期においては大変うまく適合していたものです。 世界を情緒でなく論理的にとらえることが大事であれば、千鳥に現わされているわれわれの感性(DNAにすり込まれている)について再考すべきです。 情緒は、芸術方面では決して失って欲しくないと私は 思っております。 全世界の中で縦組み千鳥の新聞は世界に誇る文化ではありますが、 しかし、私たち日本人が正しく世の中を判断してゆくには優れた論理的思考が大事だとも考えています。そのための新しい見出しの形は、情緒表現から発した千鳥ではない別の何かが必要だ、とも思っています。 今日の見出しのあり方については、レイアウトの問題と同時に新聞のアイデンティティ (=日本人のアイデンティティ)についても考えるべきだと思います。 また、千鳥によって出来る上下の間については、初期においては生かされていましたが、今の、千鳥の周りに横組みで見出しを詰め込むのは、とても美しいとは言えません。それに解りにくい事さえあります。 これに関しては美学的にも許されざるもので、日本人の大事にしてきた間の考え方から逸脱したもので、ただ空いているから見出しを突っ込んだものにすぎません。紙不足の非常時に出来た悪弊ではないかと思われます。 ちなみに私は、新聞の見出しは、「ゴチャゴチャとスッキリ」 をうまく組み合わせることが出来ないかと考えています。時間のかかる作業です。 |
||
| ■「茶室」の「チドリ」 | |||
| ●少し長いが、岡倉天心が「茶室」について書いた章からの1節を引用しておきます。日本文化と西洋の文化の違いを、室内装飾の方法の違いから見た、なんとも豪快で緻密で皮肉を含んだ分析がここにあります。 ●ここで注目しておきたいのは、「均斉を欠いている」日本の美術品の由来を考究している件(くだり)です。天心は、均斉を崩すことを茶室の美に見ており、それはそのまま「日本美」の「意匠」=デザインの技法につながっていることを喝破(かっぱ)しているのです。 ●「茶の本」は、天心が英語で書いたものを、村岡博・東京高等師範学校教授によって和訳されたものですが、同教授が「意匠」と約した原文は「Design」(デザイン)であったに違いありません。(目下、調べ中)。天心は、早くから、「デザイン」に関心をもっていたのでした。 ●「均斉を崩す」とは、すなわち、「チドリ」です! 新聞デザインの淵源には、「茶室の美意識」が働いているのです。 |
|||
| ●この一節を読むたび、新聞レイアウト・デザイン上の手法としての「チドリ」を連想しないわけにはいきません。新聞制作では、「重複」は最大の「禁じ手」であるからです。 ●重複を禁じ手とする新聞制作の現場で、2行見出しの「頭揃え」を嫌う傾向が生まれ、それはやがて「主見出し」と「袖見出し」の位置をずらし、チドリにする歴史がはじまった、と考えられるのです。 ●「茶の本」は、色の重複をはじめ、茶室の内部のさまざまな「重複タブー」を例示し、「たくさんのもの」(=重複)を壁にかけ饗宴に興じる西欧の美意識を笑っています。 ●重複を避け、なおかつ単調を避けるための茶室の工夫は、そのまま新聞制作セオリーとしての「チドリ」に繋がっているのではないでしょうか。 |
■「茶の本」の第4章「茶室」を読んでみよう! 第四章 茶室 (中略) 「数奇屋」はわが装飾法の他の方面を連想させる。日本の美術品が均斉を欠いていることは西洋批評家のしばしば述べたところである。これもまた禅を通じて道教の理想の現われた結果である。 儒教の根深い両元主義も、北方仏教の三尊崇拝も、決して均斉の表現に反対したものではなかった。実際、もしシナ古代の青銅器具または唐代および奈良時代の宗教的美術品を研究してみれば均斉を得るために不断の努力をしたことが認められるであろう。わが国の古典的屋内装飾はその配合が全く均斉を保っていた。 しかしながら道教や禅の「完全」という概念は別のものであった。彼らの哲学の動的な性質は完全そのものよりも、完全を求むる手続きに重きをおいた。真の美はただ「不完全」を心の中に完成する人によってのみ見いだされる。人生と芸術の力強いところはその発達の可能性に存した。 茶室においては、自己に関連して心の中に全効果を完成することが客各自に任されている。禅の考え方が世間一般の思考形式となって以来、極東の美術は均斉ということは完成を表わすのみならず重複を表わすものとしてことさらに避けていた。意匠の均斉は想像の清新を全く破壊するものと考えられていた。このゆえに人物よりも山水花鳥を画題として好んで用いるようになった。人物は見る人みずからの姿として現われているのであるから。 実際われわれは往々あまりに自己をあらわし過ぎて困る、そしてわれわれは虚栄心があるにもかかわらず自愛さえも単調になりがちである。茶室においては重複の恐れが絶えずある。室の装飾に用いる種々な物は色彩意匠の重複しないように選ばなければならぬ。 生花があれば草花の絵は許されぬ。丸い釜(かま)を用いれば水さしは角張っていなければならぬ。黒釉薬(くろうわぐすり)の茶わんは黒塗りの茶入れとともに用いてはならぬ。香炉や花瓶(かびん)を床の間にすえるにも、その場所を二等分してはならないから、ちょうどそのまん中に置かぬよう注意せねばならぬ。少しでも室内の単調の気味を破るために、床の間の柱は他の柱とは異なった材木を用いねばならぬ。 この点においてもまた日本の室内装飾法は西洋の壁炉やその他の場所に物が均等に並べてある装飾法と異なっている。西洋の家ではわれわれから見れば無用の重複と思われるものにしばしば出くわすことがある。背後からその人の全身像がじっとこちらを見ている人と対談するのはつらいことである。肖像の人か、語っている人か、いずれが真のその人であろうかといぶかり、その一方はにせ物に違いないという妙な確信をいだいてくる。 お祝いの饗宴に連なりながら食堂の壁に描かれたたくさんのものをつくづくながめて、ひそかに消化の傷害をおこしたことは幾度も幾度もある。何ゆえにこのような遊猟の獲物を描いたものや魚類果物の丹精こめた彫刻をおくのであるか。何ゆえに家伝の金銀食器を取り出して、かつてそれを用いて食事をし今はなき人を思い出させるのであるか。 (後略) ワイド版岩波文庫「茶の本」(岡倉覚三著、村岡博訳、岩波書店、60~62頁)より。 *原文は縦書きであり、また原文のルビを( )内に入れたり、改行、行空きを、適宜。施してあります。 |
||
| ●「チドリ見出し」が新聞に定着したのは、新聞社のマニュアルに「見出しは千鳥とする」という一条があったからのようです。はじめは、「4行見出し」などの、現在の新聞では見られなくなった「多行見出し」を「千鳥状」にしたようです。 ●その形は、「和歌の散らし書きそのものでした」と、アートディレクターの東盛太郎さんは、新聞のチドリ見出しの淵源を「散らし書き」に求めています。 |
|||
| 新聞からチドリがなくなる日 | |||
| ■新聞レイアウトの<禁じ手>という妖怪 | |||
|
●新聞組み版のセオリーとして、現在も、禁じ手・禁則とされている「伝統の技」があります。よく知られた「腹きり」などは、その代表例でしょう。 |
|||
| ■新聞レイアウトの禁じ手あれこれ | |||
| ●とはいえ、新聞レイアウトの「禁じ手」を、知っておくことは無用ではありません。 ①同じ大きさ・形(を避ける。繰り返しを避ける。) ②見出しの横並び ③門構え=罫の横並び、 ④腹きり。→毎日新聞の試み ⑤尻餅=2段以上の写真や、2段以上の見出しは、最下段に置かないという禁則。1段ものなら「まあ、いいか」と許容する向きもある。理由はない。 ⑥両落ち・両流れ・両降り。 ⑦泣き別れ。 ⑧流しとまたぎの混在。 ⑨煙突(見出し、写真)、 ⑩飛び越し。 ⑪そっぽ。 ⑫ 割り込み。 ●「⑦⑧⑫以外は、禁じ手としなくてもいいのではないか」というのが、日本新聞協会整理研究部会の見解です。 ●①②③は、「重複を避ける」というルールの一部に過ぎない。 |
|||
| ■地紋という遺物 | |||
| ●活版時代の名残 | |||
| ■新聞レイアウトの因習について | |||
| ●なぜ、新聞のレイアウトは、「禁じ手」「禁則」「タブー」を自らに課し、自縄自縛の状態を「法律」のように守っているのでしょうか。その答えは、もはや明白です。 ①因習、アナクロニズム、保守・保身、威厳の失墜への恐れ ②経験主義、「整理」の非近代性、職人主義、 ③拙速の技術としての「流したたみ」。 ④刷り込み ⑤デザイン感覚の欠如。 |
|||
| モジュール、グリッド・システム アート・ディレクション |
|||
| 質感表現の進化と切れ味の退化について | |||
| →新聞・コンテンツ百態へ | |||
