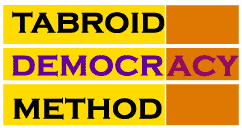 作ってみようタブロイド |
||
| タブロイド版レイアウトの技法について | ||
| タブロイドは、新聞のブランケット版ではなく、雑誌の小型メディアでもない。 タブロイド版という独自のデザイン規格であり、それ自体独立した世界である。 |
||
| タブロイドは、気ままな世界である。 新聞レイアウト(の制約)からも、雑誌レイアウト(の制約)からも、自由である。 その上、新聞と雑誌のどちらのセオリーをも許容する。 |
||
| 新聞的レイアウトとはなにか、雑誌的レイアウトとはなにか。 新聞レイアウトのセオリーとはなにか、雑誌レイアウトのセオリーとはなにか。 この二つのレイアウト・セオリーがどんなものであるかを知っておきたい。 |
||
| ここでは、朝日、読売、毎日、日経、産経に代表される日刊一般新聞のブランケット版を想定し、スポーツ新聞のレイアウトを除外しておく。スポーツ新聞のレイアウトは、一般新聞のレイアウト理論とは別個の、独自な世界を切り開いているからである。 | ||
| 一般新聞 | 一般新聞レイアウトの骨格をなすセオリーには ①「動」のセオリー=ニュースらしい紙面作り ②「チドリ」のセオリー=非対称形が生み出すダイナミズム ③読み易く正確な紙面作りのセオリー=子どもから大人まで広範な読者を想定している ……の三つのポイントがある。 |
|
| 雑誌レイアウト | 雑誌レイアウトは、フリーである。 メディアによってさまざまなレイアウトが行われているし、あらゆる紙面が、あらゆるレイアウト・セオリーを駆使しているし、メディアによって、独自で別個な世界を展開している。各メディアは、「差別化」を最大のテーマとし、「これが雑誌のレイアウトだ」といえる「制約」を受けていない。 一般新聞が、営々として築き上げてきた「割り付け理論」の歴史・伝統に制約されることによって、「新聞のイメージ」を固守してきた理由を、雑誌レイアウト・セオリーは持たない。 |
|
| タブロイド・デモクラシー | 新聞制作は「整理マン」「整理部」、雑誌制作は「デザイナー」「アートディレクター」というビジュアル担当者があることが、新聞と雑誌のレイアウトを隔ててきた。新聞作りと雑誌作りは、サッカーと野球ほどの異なる世界だった。 タブロイドは、新聞と雑誌の中間にあり、新聞と雑誌とは別個のレイアウト理論を持つに至った。2004年現在、「タブロイド・ルネッサンス」を称揚する者もいるほどに、だれもが作れる紙メディアになっている。DTPの進化、浸透を背景に、「タブロイド・デモクラシー」の時代が訪れている。 |
|
| 作ってみる前に | ||
| A3の白紙を縦に置いてみる。タブロイドとA3は、厳密には同じではないが、ブランケット版がA2に相当し、タブロイド版はA3に相当する、とひとまずは考えておこう。A3を縦に置けば、タブロイドでよし、としよう。 まっさらなA3の白紙をどのように分割するか。無限にある分割方法の中から、ある方法を選ぶのは、やさしいようでむずかしく、むずかしいようでやさしい。 カラーなのか、モノクロなのか、1ページだけ作るのか、2ページなのか、4ぺーじなのか、8ページなのか、12ページなのか、16ページなのか、ベタ文字(基本となる文字)のサイズをどれくらいにするか、字詰めは何文字にするか、横組みか縦組みか、行間はどれくらいの幅にするか、右綴じか左綴じか……などの基本設計をまず行わなければならない。 |
||
| いや、その前に、もっともっと大きなことがある。 いったい、何を作るの? ポスターなの、チラシなの、情報誌なの、新聞なの、雑誌なの……? タブロイドは、なんでもOKなんだ。どれもできるよ。 |
||
| 文字が多いの? 少ないの? 写真が多いの? 少ないの? これが、一番、大事。 文字の比率、本文比率は、「ビジュアル率」と直接に関係する。だから、本文比率ということを、まず、考えてみよう。 |
||
| 「本文」というと、そもそも、文字主体のメディアをイメージするだろう。ポスターやチラシに、「本文」という概念は、まずない。新聞か雑誌が、すぐさま思い浮かべられることだろう。 「文字組」のイメージがあり、「段組」された文字のある紙面・誌面イメージが浮かび、それらには「本文」がある。 |
||
| どうも、レイアウトがイメージ通りにいかない、という時、そもそも本文比率に無理がある場合がほとんどである。企画・編集が、よくない場合がほとんどと言っても過言ではないから、文章を削ったり、紙・誌面スペースを増やしたり、写真を増やしたり、イラストを描いたり……して、とにかく、本文比率を下げる作業を行うとよい。 | ||
| この作業を、編集という。 編集は、レイアウトやデザインといった紙・誌面制作よりも上流にある工程だから、レイアウターやデザイナーはその権限を持たないし、立ち入れない、といって引っ込むことはない。レイアウトやデザインが、紙・誌面のビジュアルを担当する工程であるからといって、編集権者との協働作業を放棄してはいけない。 編集に投げ返す、という作業は、レイアウターやデザイナーのれっきとした仕事とみなそう。紙・誌面づくりは、編集権者の指示の範囲にありながら、両者の協業であることを理解すべきである。対等ではあり得ないが、紙・誌面づくりという「現場」では、提案や相談や議論を排除すると、ろくなことにならない。 「甘い」「辛い」は、はっきりと、編集者に伝えよう。その場合の、キーワードが「本文比率」である。 |
||
| 「本文」は、段組された本文記事だけを指す。 見出し、写真説明、前文(リード)、写真、イラスト、表・グラフ、広告、題字など、まさに、段組された本文をのぞいたすべての素材が、「本文以外」である。 本文÷本文以外=本文比率。 本文比率が高い紙・誌面を「辛い」、逆に、本文比率が低い紙・誌面を「甘い」などと、新聞整理の世界では言う。 「辛い」場合は、記事を削除、「甘い」場合は記事を加える――のが原則だ。 しかし、ここが、ポイント! 「ビジュアルな」紙・誌面にしたいなら、「甘い」ままのほうがベターなのだ。 ①甘ければ、写真を使える ②甘ければ、見出しを大きく扱える ③甘ければ、余白ができる つまり、「甘い」は、ビジュアル化の一歩である。 |
||
| 本文と「本文以外」の比率を、仮に、本文比率と呼んでおく。 チラシやポスターやグラフィックな紙・誌面は、本文という考え方がないから、本文比率はゼロである。 |
||
| この辺で、タブロイドの実際を見てみよう。毎日毎日、朝刊とともに「折り込まれて」くる「チラシ」は、ほとんどがタブロイドのコンセプトによって、作られていることがわかる。ブランケット版の一般新聞でさえ、印刷の版形はブランケットであるにもかかわらず、実際には、その半分に折られて、タブロイドの大きさで配達されている。 | ||
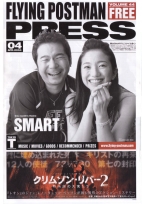 |
||
 |
||
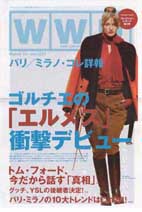 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
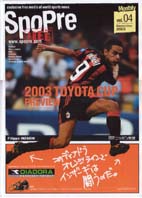 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||